我々の死者と未来の他者 戦後日本人が失ったもの 大澤真幸 を読んだ。
文章っが読みやすく、面白かったです。
大澤真幸さんの本で読んだことのあるのは、橋爪大三郎さんと共著の「不思議なキリスト教」がある。キリスト教特に福音派系の信者さんから多くの批判がでた本です。
第1章は、「鬼滅の刃」から話が始まります。私は「鬼滅の刃」や「おしん」を読んでいないのですが話にはついて行く事が出来ます。
最初に日本人が気候変動等に対して、他の先進国との比較で異常に無関心だということがグラフ等で説明されます。地球温暖化で最も被害が現れるのは、我々がこの世に居ないだろうと思われる西暦2100年です。つまり地球温暖化の被害を受けるのは我々ではなく、「未来の他者」である事。そして、なぜ今生きている我々が、将来の我々が生きては居ない時代の「未来の他者」の問題に無関心なのか?その理由は日本人が我々の死者を失ったからだと言います。ではいつ、どのような理由で日本人は「我々の死者」を失ったのか、それは「戦後の日本人は、戦前の他者たち、とりわけ戦争で死んでいった者たちが実現しようと願っていたもの、彼らがそのために死んでいった「大儀」をそのまま肯定的に継承し、それを完成しようと努力するわけにはいかない。敗戦を通じて、日本人は、自が追及してきたことが過ちであることを学んだからである。戦争前の死者たちの願望や希望を、現在の我々は、打ち捨てなければならないのだ。」といいます。
第2章は、太宰治の短編小説「トカトカトン」「散華」等の短編小説の話。私は中学生のころ太宰治を読んでいた。「トカトカトン」は印象に残っています。
その小説「トカトカトン」を通じて、戦後「我々の死者」を失った現在の我々の気分を説明しています。どこからか「トカトカトン」と聞こえてくる。この音が聞こえると、それまで一生懸命に取り組んできたことが突然と無意味になる。「トカトカトン」は終戦時一夜にしてこれまでの良いとする事が悪に代わる感覚を表し、今後もその様な事が起きる予感を描いている。
第3章は、加藤典洋の「敗戦後論」の話。私は読んだことはない。しかし話にはついて行けました。
アジア・太平洋戦争での「アジアの犠牲者」への謝罪がアジアの国々で受け入れられない理由が説明されている。謝罪と赦しの話です。
第4章は、鶴見俊輔と吉本隆明が出てくる。鶴見俊輔は名前だけは知っている程度。吉本隆明は「共同幻想論」を読んだが全く記憶に残っていない。
両者の終戦前後の考えの変化を説明している。鶴見俊輔の分析では戦前・戦中に現在の我々がその思いを引き継ぐことが出来る「我々の死者」がいた、吉本の分析ではそれは無い。えはどうすればよいのか?
第5章では、司馬遼太郎の一連の歴史小説の話です。私は本書で出てくる小説を読んでいるために分かりやすかったです。
司馬遼太郎の最も現在に近い歴史小説は「坂の上の雲」です。それ以降の時代、昭和についての文章は発表しているのにも関わらず歴史小説は書かなかった。なぜ司馬遼太郎が、満州事変、モノンハン事件について書かなかったのか或いは書けなかったのか、との話です。
第6章では主に、村上春樹の「ねじ巻鳥クロニクル」が出てきます。彼の小説は一部を除いて読んでいます。
この小説は、司馬遼太郎が書けなかった、モノンハン事件の話が出てきます。この小説は「我々の死者」を取り戻す試みとする立場からの小説の解説です。
本書を読んでいて感じたことは、時間・歴史の感覚が、教義的キリスト教ではなく聖書的なキリスト教の感覚だと感じた。
また、現在の日本の憲法を明治憲法に戻す復憲論と現在の日本憲法の存在を認めて一部改正で良いと考える改憲論も、「我々の死者」のとらえ方の問題がある様に感じた。さらに、現在のドイツで行われているイスラエル擁護の運動もそうかなと思った。
にほんブログ村
本・書籍ランキング
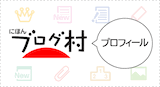





0 件のコメント:
コメントを投稿