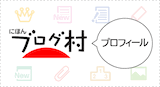「主権者を疑う ―統治の主役は誰なのか?―」駒村圭吾著を読みました。税込み1、012円です。 ★★★☆☆
著者の駒村圭吾さんは1960年東京生まれの憲法学の法学博士です。憲法学といえば土井たか子さんですね。ネット動画のデモクラシータイムスの 平野貞夫さん×前川喜平さん×佐高信さんが出演している 3ジジ放談 で平野貞夫さんが、あの浜田幸一さんが土井たか子さんのファンで、そのエピソードを話していた。土井たか子さんの本会議等での演説中に自民党の議員が野次を飛ばしていた。その野次が五月蠅く、土井たか子さんの演説が聞きづらいので、自民党席に向かって静かかにするように言ったらしい。その忠告に対して自民党からクレームが付いたので、浜田幸一さんは、静かにしなさいと紙に書いて配ったとのエピソードを話していた。
本書の目次。
はしがき
序 章 見取り図 ― 日本国憲法に登場する「国民」たち
第1章 主権者Part 1 ― ロゴスと意思
1 「最終的に決めるのは、主権者たる国民の皆様であります」
改憲論議を振り返る―主権論の〝重さ〞と〝軽さ〞/国民投票の「権利」の剝奪?
2 主権についての伝統的理解
主権の三つの相/最高権力の源泉としての「最高の意思力」
3 ロゴスから意思へ
神の至高性と三位一体論―「ロゴスとしての神」とその万能性・永遠不変性/神、理性、意思―トマス・アクィナス/普遍か個物か、理性か意思か―スコトゥスとオッカム/神の意思の絶対性と恣意性
4 至上権争い ― 神権と俗権の攻防
神学から政治思想へ/両剣論―神権と王権の区別/教皇至上権へ
5 中世の解体と主権論の浮揚
教皇の没落と中世の解体/主権論と「王権の自律」―家族・教会・国家/神を演ずる王―王権神授説の専制化/中世神学の「反転応用」としての主権論/主権と法―至高性を枠づけるもの
6 本章のまとめ
第2章 主権者Part 2 ― 忘れられた巨人
1 破壊者=創造者
〝破壊者=創造者〞としての神 ― 大魔神・ゴジラ・宇宙人
2 〝破壊者=創造者〞としての「憲法制定権力」
憲法制定権力とは/〝破壊者=創造者〞としての制憲権
3 主権者をおさえ込む?
超越的規範に訴える―自然法論の系譜と主権者の自己拘束/主権者の出番を少なくする―制憲権の常駐か封印か/主権の独占を許さない―意思主体か代表機関か
4 国民主権論はなぜ受け容れられているのか?
国民主権がはらむいくつかの問題/国民主権論とはどういう企てなのか
5 アメリカの経験から
「人民主権」と「州主権」/チザム対ジョージア事件判決(1793年)/チザム判決個別意見に見る初期アメリカの主権論/連邦法無効宣言危機/奴隷州、自由州、人民主権/南北戦争の遺産―「失われた大義」
6 主権と主権者
主権者の神格化/天皇機関説事件/ヤングスタウン鉄鋼所接収事件アメリカ最高裁判決(1952年)/主権が人格化するとき ― ジャクソン補足意見の主権論/主権的人格への帰依か、最後の理性か/主権者は誰でもいい?―尾高=宮沢論争/主権抹殺論?/ノモス主権論の含意/神話の密輸入
7 本章のまとめ
国民主権は解決にならない/では、どうするか/忘れられた巨人
第3章 民主主義
1 原風景としての「民衆支配」
Democracy の原義にさかのぼる/堕落した統治形態の中では民主制がベスト/民主制の本質は〝衆愚〞である
2 〝衆愚〞その1 ― 愚民とエリート
雄蜂と哲人―プラトン/愚民とエリートの分断を超えて
3 〝衆愚〞その2 ― 主権者としての「大衆」
アレントの「モッブ」/「大衆」の登場/平均人の巨大な波―オルテガの大衆論/平均人・普通人の磁場/主権者としての大衆
4 魔術から計算へ
情報環境の今昔/デイリー・ミー→エコー・チェンバー→集団分極化―サンスティンの#リパブリック論/集団分極化―デジタル社会の「雄蜂の群れ」・「モッブ」/〝主権者国民〞の分極化・均質化・可視化/魔術から計算へ―「一人一票」制という変換ツール/東浩紀の「一般意志2.0」/熟議と計算の対抗
5 「選挙こそがすべて」……なのか?
すべてが政治、最後は選挙?/選挙の実相―ロンダリングの回路が生み出す時限的独裁/計算結果の専制
6 民主主義という〝利益相反〞
「自己統治」という言葉について/代表制という〝利益相反〞/まずは、あからさまな利益相反をどうにかしよう
7 民主主義の再設計
ここまでの流れの整理/アルゴリズム/くじ引き/国民投票/法の支配/民間法制局?
第4章 市民社会
1 砂川判決再訪
砂川事件とは?/9条の命運(その1)―解消されない憲法上の疑義/9条の命運(その2 )―ふたつのオプションの並置/9条の命運(その3 ) ―主権者国民の政治的批判?
2 「主権を有する国民の政治的批判」
「社会の雑音」―田中耕太郎長官との対峙/岸盛一裁判官の場合/富川秀秋裁判官の場合/憲法の正統性危機と国民の批判的活動
3 市民運動の来歴と「動員の革命」
日本の市民運動が熱かったころ/最高裁の〝集団暴徒化論〞/SNSによる「動員の革命」/「動員の革命」の失敗―宇野常寛の問題提起
4 デモの祝祭性と日常性
デモの近未来を考える―〝動員〞と〝人流〞をめぐって/非日常性の強化・洗練と日常性へのはたらきかけ/他者の存在確認と自己の存在証明のためのデモ/つかの間の自由としてのデモ―小田実とG・ルフェーヴル/身体を差し出す―J・バトラーのアセンブリ論/凶兆としてのデモ
5 〝市民社会〞の近未来
アイデンティティ・リベラリズムの陥穽― M・リラのリベラル批判/「市民」という身分の復権/「名刺交換をしないデモ」という「無知のベール」/分人民主主義というコペルニクス的転回―鈴木健の挑戦/近未来の統治
あとがき
日本国憲法 抄録
参考文献
索引
主権をキリスト教の新約聖書の中に文書の一つであるヨハネによる福音書の「初めに言葉があった。言葉は神とともにあった。言葉は神であった。」を解釈したアウグスティヌスの教説から、その後の時代のスコラ哲学、現代の裁判事例等の歴史の流れに沿って説明している。主権とは、聖書、特に旧約聖書に登場する創造者=破壊者としての神の絶対性に由来している。読んでいて聖書の神に馴染みのない日本人が、ユダヤ・キリスト教に馴染みのある人たちの歴史から生まれてきた主権という考え方に馴染めるかとが疑問に思った。
安倍晋三さんは総理大臣就任中に主権者についての発言を繰り返していた。【「憲法改正は普通の法律と違い、最終的に国民が決定権を持ちます。現行憲法が施行されて70年以上たちますが、一度も国民投票が行われていない。私たち国会議員が発議を怠り、国民に権利を施行させないことは「国民に対する責任放棄だ。」とそしりを免れない。」(2018年9月1日産経新聞のインタビューに答えて)。「最終的に決めるのは、主権者たる国民の皆様であります。」(同)「『安倍晋三が嫌いだ』と言って国民から国民投票の権利を奪うのはサボタージュではないでしょうか」(2019年1月4日年頭記者会見 2018年12月10日)総理記者会見)】(p023)この発言の中の「国民」を聖書の神と同等な存在として想像することは難しいように思える。
憲法・法的なものを、ほぼ初めて読んだのですが、歴史的な部分は面白く読めました。スコラ哲学の話、王権神授説、アメリカの事例、砂川判決等の日本の事例等もわかりやすく書かれています。今後の事についてのの提案は、「なんだかなー」感があった。